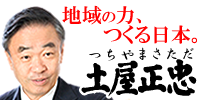武蔵野市にはライドシェアの先行例があります。23年前から始まったレモンキャブです
国会でライドシェアが議論されています。武蔵野市では、市と市民が協働で23年前からレモンキャブというシステムを運行しています。
レモンキャブの概要
●30分800円で自宅まで送迎。病院や介護施設・文化施設や買い物にも利用できる。
●会員制で利用者は社会福祉協議会に登録して利用する。年間登録料1000円。
●車両は軽自動車リフト付き。車イスも利用可能。武蔵野市が購入して無償で運転管理者に貸し出す。
●運転管理者は、お米屋さんや燃料屋さん等の商店経営者やその関係者。
●1車輌あたり1名の運転管理者と複数の協力員が交代で運転して、月~土曜日運行
●経費の区分は、車両購入費・車検・ガソリン代・保険料などは武蔵野市負担。利用者は30分800円を負担。この利用料は運転者の収入となる。
●利用開始は平成12(2000)年で車両数9台(900人の登録利用会員。運転管理者と協力員が40名余り)で、利用実績は延利用回数が15000回/年。
●法的根拠は道路運送法第78条。自家用車両の有償利用制度。
なお車両は8年または10万kmを目安に買い替えています。
武蔵野市と市民が協力した公民連携の安心のライドシェアです。最小の経費で最大の効果を挙げています。