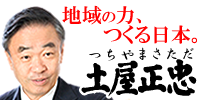東京都は今年の秋頃から財政がひっ迫して火車になるのではー小池さん都基金(貯金)を9000億円使ってしまって大丈夫?
令和2年度の東京都の一般会計予算は7兆3540億円です。歳入の大宗をなす都税5兆5032億円のうち法人二税が1兆7996憶を占めている。法人二税は現年度の所得に課税するのだから現在進行形で経済の動きに連動している。コロナ感染症の影響で法人所得は激減するのでは?今年の秋頃になると姿形が見えてくると思うのだが、法人二税が約1兆8000億円が半減するのではないでしょうか。その時基金がゼロ近くになってしまっては予算の執行が出来ない。小池知事どうしますか。
都議会が5月27日から始まった。6月2日が代表質問の日程だが、どのような論議が行われるのだろうか注目です。