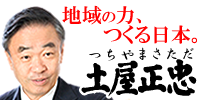ゼレンスキー大統領はネットを通じて、避難してる子どもたちに呼びかけた。やがて故郷に帰れる日が必ず来る
ウクライナの国外と国内で、戦災をさけて避難している子どもたちは数百万人におよぶとのこと。ゼレンスキー大統領は珍しく笑顔で呼びかけました。映像からは故郷に帰れる日が来るために戦っているという気持ちが伝わってきました。子どもたちにとっては、何よりのメッセージになったことでしょう。
戦争中のウクライナから、ウクライナ国民と周辺国の国民にSNSを使用できるのは、2月末にイーロン・マスク氏が提供したスターリンクのネットワークとそれを使用できる端末数千台が役立っている。
重厚長大なロシア軍と最先端のネットワークを駆使するウクライナの勝負は、ロケット砲と戦車だけでは決まらない。