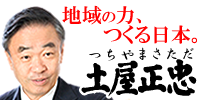スマホを捨てたい子どもたち―野生に学ぶ「未知の時代」の生き方―山極壽一前京大総長
自民党政調教育再生委員会で山極先生をお招きしてスマホ時代の教育の在り方について、お話を伺いました。
山極先生は文化人類学の泰斗で、人間に近いゴリラやオランウータンの生態を観察し、人間が700万年かけて進化し現代人まで歩んできたことの意味を問い続けてきた総合知の巨人です。
山極先生はゴリラの研究で小学生中学生に呼ばれることが多いが、若い世代に友人は何人?と聞くと3~5人という子供も多い。スマホをツールにして相当多くの人と繋がっているが、友人と呼べる人は少ない。生まれながらスマホのある生活をしている世代は、スマホを捨てたがっていると観察しているとのこと。
●人類の歴史は700万年前に二足歩行したことに始まる
●400万年前の脳の容量は600cc
●脳の容量が現代人並の1500ccになるのは40万年前
●この頃、集団的狩猟が始まった。やがて火の使用、宗教、言葉の発明、農業へと繋がっていく
●言葉の発明は2万年前、文字の発明は5000年前、電話は150年前、インターネットの発明は40年前だ
●言葉が脳を大きくしたのではなく、脳が大きくなった結果生まれた社会脳仮説と言われるが、今は大多数の学者が肯定している
●人間の脳は1年で2倍、チンパンジーは4年で2倍、チンパンジーは授乳期間が長い! 人間は1年なので次の出産が出来る
●子どもの成長期には2つの危ない時期がある。離乳期(2~6才)と思春期(12~16才)
●人間の集団規模とコミュニケーション
①10~15人 共鳴集団 言葉が要らない
②30~50人 顔と性格を熟知して一致して動ける。学校の級や軍隊の基礎単位
③100~150人 信頼出来る仲間 顔と名前が一致
④それ以上になると身体以外の指標が必要。この150人というのは、現代の狩猟採集民の集団規模の平均値である
●信頼は身体の同調によって育まれる社交が重要。社交はリズムである
●共感能力が高まった背景は共同の食事と共同の子育て、家族と地域社会
●情報革命、AIに支配されないために
●コロナ禍の教訓。動く自由、集まる自由、対話する自由、遊動の時代
以上30分のスピーチと1枚のレジュメに基づいてメモしましたが、実に示唆に富むお話でした。